社会とLCA研究グループ
社会とLCA研究グループ

研究職員:5名
櫻井 啓一郎 小野 恭子(兼務) 小島 直也(兼務) Chun Yoon-Young(兼務)
契約職員等:5名
概要
社会の変化に伴って導入された新しい技術がもたらす可能性のある問題について、リスク評価およびライフサイクルアセスメント(LCA)を実施し、自治体の脱炭素化計画策定、持続可能な社会の実現に向けた制度設計支援につながる研究を行っています。特に化学物質に関して、製品のライフサイクル全体を考慮したリスク評価・リスクトレードオフ解析、災害や事故のリスク評価に関する技術開発に取り組んでいます。また、社会経済への影響や波及効果を分析する評価手法の開発や、社会受容性の調査・分析も行っています。太陽光発電技術、エネルギー回収技術、再生プラスチック・海洋生分解プラスチックの導入など、幅広い分野を対象として扱っています。さらに、多くの産業の基盤となる統計的方法についても研究を進めています。
研究内容
再生プラスチックのリスク評価
プラスチックの資源循環の加速化にあたり、再生プラスチック素材に含まれる化学物質(添加剤や汚染物質)による健康影響について、リスク評価が求められています。プラスチックの使用後を含めたライフサイクルを把握すると共に、それらの化学物質について、暴露評価、リスク評価を実施し、管理手法の提案を目指します。
 |
再生プラスチックに関するリスク評価の枠組み
アンモニアのリスク評価・リスク管理手法評価
将来、大量貯蔵・使用が見込まれる燃料アンモニアについて、事故時のアンモニア漏洩による事業所周辺へのリスクの評価枠組みを設定し、リスク評価を実施します。特に日本においてデータが不足している漏洩事故の発生確率については、アンモニアの漏洩事故データからベイズ推論を用いて、漏洩規模ごとに頻度を推定します。定量的リスク評価結果を提供することにより、合理的な意思決定を支援します。
 |
アンモニア燃料船における漏えい頻度推定の概要
エネルギー技術普及加速方策の検討
低炭素化を進めて持続的な社会に変えていくには、建造物の断熱、再生可能エネルギー、電気自動車等の技術そのものの開発のみならず、それらをなるべくスムーズにかつ速やかに普及させる方策も大切です。科学的な裏付けのある情報の共有、人材育成、融資の確保、地域の産業構成や風土との適合等に配慮しながら普及を進め、便益を最大化するための研究を進めています。
 |
図 2050年時点までの世界の太陽光発電の導入ペースの目安
(N.M. Haegel et al., Science 380, Issue 6640, pp. 39-42, 6 Apr 2023)
今後10年間で年間導入設備量を10倍程度まで拡大させることで、持続的な社会において必要と想定される規模の導入設備量(この例では2050年時点で75TW)に達します。これまでの実績と今後の見通しからは、この目標は達成可能と示唆されます。
放射能廃棄物を活用したエネルギー回収技術に対する社会的受容性分析
放射性廃棄物からのエネルギー収穫技術は、革新的で持続可能なエネルギーソリューションになり得ます。しかし、放射能廃棄物やその活用技術に対する公定的な認識と低い受容度は、技術を実現するための障壁となる可能性があります。本研究では、放射性廃棄物を活用したエネルギー回収技術に対する公衆の受容性、態度、認識を理解し分析するためのモデル構築を行っています。
 |
放射能廃棄物を活用したエネルギー回収技術への受容意向分析モデル
統計的方法の適用に関する国際標準化活動
統計的品質管理をはじめ、多くの産業の基盤となる統計的方法の適用は、国際標準化機構第69専門分科会(ISO/TC69)において標準化が進められています。この活動に深く関わっており、統計用語や記号、データの統計的な解釈方法、測定(試験)方法の精度を定量化する統計的手法などの国際的なルール作りに貢献しています。また、この活動における議論の中で必要となった関連手法の研究にも取り組んでいます。
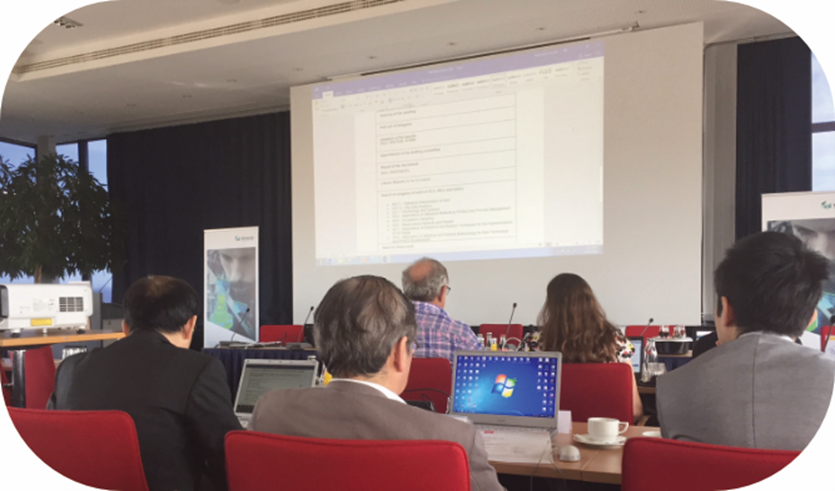 |
ISO/TC69総会の様子
研究紹介

